
発行の背景
- 明治4年(1871年)に「新貨条例」が制定され、金本位制に基づく金貨が発行された。
- しかし旧10円金貨(1871~1897年発行)は重量が大きく、国際的な金の価格水準に合わず流通に不便。
- 1897年の貨幣法改正で金本位制を強化し、金貨の量目や純度を変更。
- その際に造られたのが「新金貨」と呼ばれるシリーズで、その中に10円金貨が含まれる。
基本スペック
- 額面:10円
- 発行期間:1897年(明治30年)~1910年(明治43年)
- 量目:8.33グラム
- 直径:21.21ミリ
- 品位:金900(純金90%、残りは銅など)
- 形状:円形


デザイン
- 表面:菊花紋章、桐、唐草模様、左右に桐紋
- 裏面:十円の文字、日章、菊と桐の組み合わせ、稲の穂、年号(明治○年)
(旧10円金貨より小型・軽量になったのが特徴)
歴史的な位置づけ
- 「新10円金貨」は、旧金貨制度を改めた最初の大型金貨の一つ。
- 実際には当時の購買力では庶民にとって超高額だったため、流通は限られ主に銀行や大口取引で使用。
- 1910年(明治43年)に発行が終了し、その後は実際の流通よりも金準備や国際決済用の性格が強かった。
現在の評価・価値
- 収集価値が高い:年代や保存状態によって十数万円~数百万円の価格で取引される。
- 特に未使用(MS級)や希少な発行年は高額。
- 地金価値(金相場)としても約8.3gの純金を含むため、最低でも金相場に連動した価値がある。


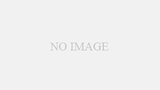
コメント